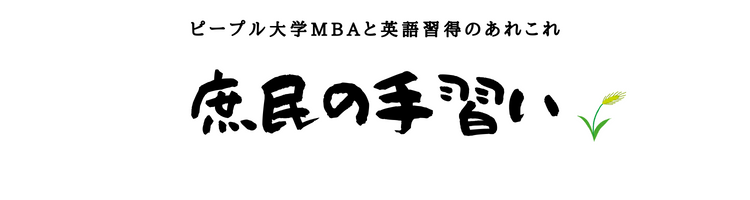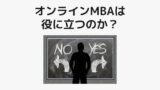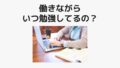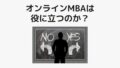コースデータ
| 区分 | 必修 | 受講時期:2024/9/5 – 2024/10/30 |
| 受講前提 | 必修 8 + 選択 3 | 11コース完了後、最終コースとして受講 |
| 難易度 | ★★★ | ※個人の感想です |
| クラス生存率 | 81% | DA8週目生徒数(22) ÷ DA1週目生徒数(27) |
| 学習時間 | 147時間 | 18h/週 * 8週間 |
シラバス:BUS 5910 Management Capstone
コース概要
キャップストーンコースは、8つの必修コースと3 つの選択コースを修了した後に、最終関門として受講するコースです。具体的には、これまでMBAプログラムで学んだ内容を、実際の組織問題に適用する能力が試される場です。
毎週のディスカッション課題は、基本的にこれまで学んだことの復習が中心となりますが、筆記課題は累積的に進み、各週の完了した作業が次の週の要件の基礎となります。そのため、各週の課題要件に従ってコース終了に到達する事で、最終レポートに必要なコンテンツの大部分が完成します。
このコースでは7 週目以降に、コースインストラクターへの最終レポートのオンラインプレゼンと質疑応答があります。
- 組織理論
- 根本原因分析、プロブレム・ステートメント(5W1H)
- 組織理論と人的資源
- 5Why分析(なぜなぜ分析)、フィッシュボーンチャート(特性要因図)
- 動機づけ理論
- プロジェクト・マネジメント
- シックス シグマ
- 財務諸表の解釈と分析
- オペレーションズ・マネジメント
- 品質問題の分析
- 企業法務、倫理
- グローバリゼーションと文化的知性(CQ)
- リーダーシップ スタイルとコミュニケーション
受講後の感想
キャップストーンコースはピープル大学MBAの最終関門であり、思っていたよりも大変でした。私は自分が受講したピープル大学 MBAの各コース生存率を、Discussion Assignment の8週目生徒数 ÷ 1週目生徒数として記録してます。後半10、11コース目のクラス生存率は100%でしたが、12コース目のキャップストーンの生存率は 81% (22人 ÷ 27人)でした。11コース全てを完了させ、ここまでたどり着いた生徒でさえ、約2割が自らコースドロップしてますので、キャップストーンコースの大変さが想像できるかと思います。
キャップストーンコースが大変な理由は、各週の課題を積み上げて最終レポートの完成を目指す、「積み上げ型」コースであることに起因すると思います。コース前半は、最終レポートの題材とする組織の背景、選択理由、プロブレム・ステートメント、根本原因分析と進み、中盤から後半にかけて、具体的施策や文献レビューに推移していきますが、コース前半で最終レポートのテーマ選びと現状分析がしっかり定まらないと、各週の課題が「独立」しているコースとは異なり、後から巻き返すのが難しくなります。
私の場合、本業であるデジタル・トランスフォーメーションと組織変革をテーマに選びましたが、これら前半のプロブレム・ステートメントや根本原因分析には大変苦戦し、筆記課題の講師評価は、第1週 7.80、第2週が8.00、第3週7.80と散々でした。ちなみに、ピープル大学 MBAのキャップストーン・コースでは、B(3.00)以上を取らなければ修了できず、これは Grade に換算すると8.00以上となります。そのため、前半戦はかなり焦りました..。
幸いにも私のコースインストラクターは、率直に良い点、悪い点を明確、かつ丁寧に示してくれる方であり、とても納得できるフィードバックをいただける方だったのですが、とはいえ、先週の問題点の見直しと修正(やり直し)をしながら、かつ今週の課題もこなしていく事は、なかなかに圧倒される、ストレスの高いプロセスでした。
しかしながら、これら困難なプロセスは、理論を実務に落とし込む訓練としては、非常に価値のある経験だったのではないかと思います。
注意が必要なポイント
キャップストーンコースで演習内容について、シラバスには詳細な記載は無く、私の場合、コースインストラクターから個別で長文のガイドラインが案内されました。これは、おそらくキャップストーン詳細は受講時期によって頻繁に変わるか、もしくは、コースインストラクターにある程度の自由裁量が認められているのかもしれません。したがって、注意が必要なポイントには、全般的に共通すると思われる事項を記載します。
時間管理
もし可能であれば、キャップストーンコースは業務の繁忙期と重ならないよう、スジュール調整されることをお勧めします。私の場合、業務繁忙期と重なってしまい、かなり苦労しました。毎週の筆記課題は次の週の課題との連続性がある設計なので、手戻りが生じる新たな課題との並行作業となり、取り返すのが難しくなっていきます。アウトプットイメージをつかむために、筆記課題の全てのルーブリック(第1週から第8週まで)を、できるだけ早いタイミングで、しっかりと読み込んでおくことをお勧めします。
最終プレゼンのタイミングは、私の場合、7 週目と 8 週目にかけて実施されました。時差はインストラクターの所在地や都合にもよりますが、米国東部標準時(EST)の場合、日本との時差は13-14時間なので、早朝か深夜での実施となります。できればプレゼンの2週間前からは、資料作成とリハーサルのためにまとまった時間を確保できるよう、前もって職場や家族に協力を依頼しておけると良いです。
コース内容への準備
過去に履修したコースのうち、経営戦略論、組織行動理論、人的資源管理、リーダーシップ論の主要フレームワークは、事前に復習しておいた方が良いです。キャップストーンの最終レポートでは、これらの概念を基盤として活用する機会があります。
根本原因分析(RCA: Root cause analysis)については、新たな読書課題があります。このテキストはAmazon等で買う場合、Kindle版でも約1万円する高額な書籍ですが、もしUoPeopleのMoodleにログインできる方であれば、オンライン ライブラリで無料で読めますので、事前に内容を確認される事をお勧めします。
参考書籍:Root Cause Analysis: The Core of Problem Solving and Corrective Action (English Edition)

参考書籍はUoPeopleのIDがあり、Moodle にログインできる方であれば、LIRN (LIRN Library and Information Resource Network) ページ上部の「Alphabetical View」をクリックして「Ebook Central」を選択。検索バーに書籍タイトルをコピーして検索することで、無料で読むことができます。
プレゼンテーション
プレゼンは、最終レポートの概要をコースインストラクターに説明し、質問に答えるために実施されます。私はスライドごとにポイントの箇条書き + 補足テキストの構成で、ストーリー性を重視して作成しました。
私の場合、特に根本原因分析と代替案についての質問が多く投げかけられました。それら質問に適切に対応するためには、自分の提案の前提条件や、それぞれの代替案のメリットとデメリット、評価軸についても、しっかりと整理しておく必要があります。
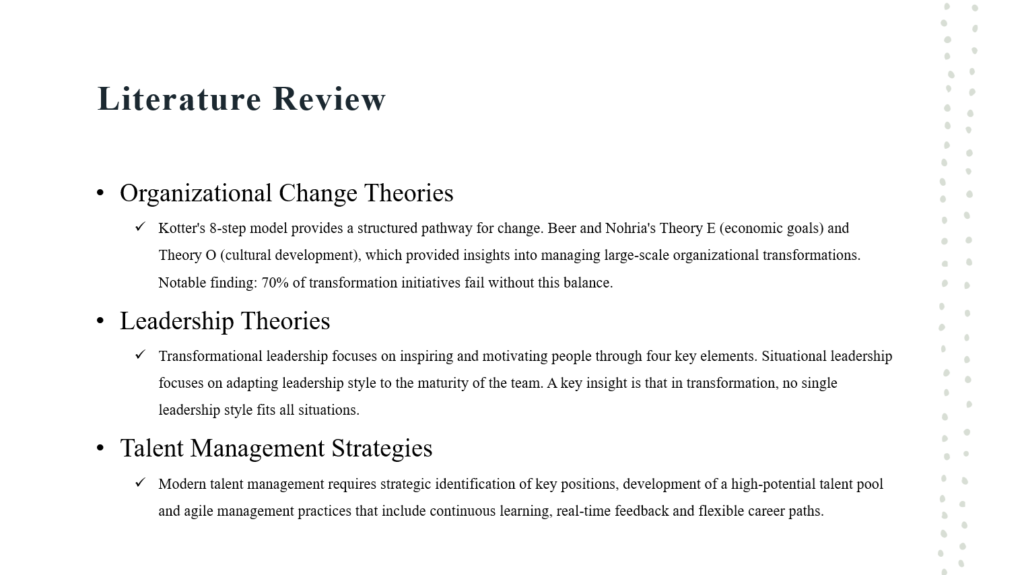
テクニカルな問題を避けるため、使用するビデオ会議システムの操作には事前に慣れておくことをお勧めします。私は講師が指定したプラットフォームを相当久しぶりに使ったため、本番でスライドの共有に手間取り、貴重な時間を失ってしまいました。
私はコースインストラクターへのオンラインプレゼンに関しては、前半戦とは打って変わり、満点をもらう事ができました。これは、前半でプロブレム・ステートメントと根本原因分析に苦しんだ分、それらがしっかりと体系的に頭の中に叩き込まれ、その後の具体的施策や文献レビューとの整合性がしっかり取れたものとなったために、あらゆる質問に自信をもって回答する事ができたためだと思います。
まとめ
前述の通り、私はキャップストーンの前半戦では大変苦しみました。しかしながら、4週目以降の課題ではほぼ満点に近いスコアを獲得することができ、最終的なコース評価はA-(3.67)まで回復させる事ができました。
フルタイムで働きながら、キャップストーンコースを乗り切るのは大変です。しかしながら、振り返ってみると、この集中的なコースが最後にあるからこそ、MBAで学んだ理論を、応用可能な知識にできるのではないかと感じます。
お役立ち情報
これで全コースが完了しましたので、UoPeople MBAで得られたものを記事に纏めました。