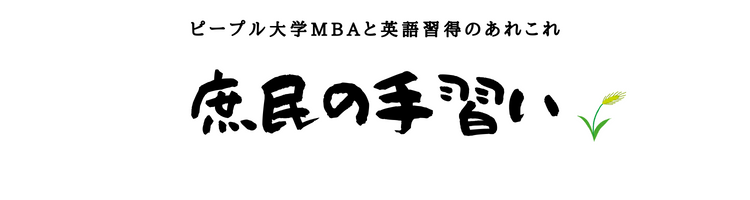コースデータ
| 区分 | 選択 | 受講時期:2023/9/8 – 2023/11/2 |
| 受講前提 | 基礎3科目 | 管理会計、マーケティング、組織行動論 |
| 難易度 | ★★ | ※個人の感想です |
| クラス生存率 | 92% | DA8週目生徒数(23) ÷ DA1週目生徒数(25) |
| 学習時間 | 92時間 | 12h/週 * 8週間 |
シラバス:BUS 5411-01: Leading in Today’s Dynamic Contexts
コース概要
本コースでは、「リーダーシップ理論」や「リーダーシップスタイル」の類型、特徴、トレンドなどを学び、ケーススタディや自身の経験にそれらをあてはめ、個人の特性、チームマネジメント、プロセス、リソース調整などの観点から「リーダーシップ」という機能や資質、能力を考察していく事で、現代の組織における、リーダーシップのあり方に対する考えを深めていきます。
本コースでは自身のリーダーシップスタイルの簡易的なアセスメントも実施しますので、実務において他者をリードする、自分のスタイルやスタンスを考えるきっかけにもなります。
- リーダーシップ入門
- 特質理論、Kurt Lewin(クルト・レヴィン)のリーダーシップスタイル類型
- 偉人理論(The Great Man Theory)
- レヴィンのリーダーシップ類型:専門型・放任型・民主型
- コンディンジェンシー理論とSL理論(条件適応理論)
- フィードラーのコンディンジェンシーモデル
- ハーシィ&ブランチャードの条件適応理論
- 行動理論、参加理論
- 行動理論:課題志向、人間関係志向
- 参加理論:民主型リーダーシップスタイル
- 取引・交換(トランザクション)理論、変革型リーダーシップ理論
- 変革の段階とリーダーシップスタイル
- Planning, Enabling, Launching, Catalyzing, Maintainningにおけるリーダーシップスタイル
- サーバント・リーダーシップ
- リーダーシップの将来動向
受講後の感想
「マネジメント」と「リーダーシップ」は似た概念であり、これらの言葉を適切に使い分けている人は少ないように思います。私もそうでした..。
ご参考までに、それぞれの言葉の定義は以下の通りです。
マネジメント:ドラッカー(Drucker)の定義
「組織として成果を上げさせるための道具、機能、機関」
Schoo. (2022, May 24). リーダーシップとマネジメントの違いとは?ドラッカー流リーダーシップの定義や特徴・スキルアップの方法を解説. Schoo for Business. https://schoo.jp/biz/column/720
リーダーシップ:ノースハウス(Northous)の定義
「集団目標の達成に向けて、個人が集団の諸活動に影響を与えるプロセス」
Benedictine University. (2017, August 15). Five Leadership Theories & How to Apply Them. Center for Values-Driven Leadership. https://cvdl.ben.edu/blog/leadership_theories_part1/
どちらも「組織成果や目標達成のため」という点は同じですが、私の個人的な解釈を会社組織に当てはめて補足説明すると、管理職は「マネジメント力」と「リーダーシップ」のどちらも発揮する必要があり、フォロワーである部下も「リーダーシップ」を発揮する事ができる、という事ではないかと思います。そして、それができる組織が強い組織なのではないでしょうか。
個人的な能力や業績を評価され、それにより出世して管理職になったような方は、部下は自分の経験から育成し、指導すべき存在と思ってしまうかもしれません。しかしながら、部下の立場でかつて上司から受けた指示を思い返してみると、「時代や状況が違うのでは?」とか、「現場がわかってないのでは?」という違和感を感じた事がある方も、実は少なくはないのではないでしょうか。
私のかつての取引先のある管理職の方は、新たなIT技術の導入による、業務プロセスの抜本的な改革(BPR)に、とても躊躇されてました。その理由は、「部下が自分の理解できない技術で、新たなプロセスで仕事を始めてしまうと、自分が部下を管理できなくなるから」だそうです。
これは、部下は自分が育成、指導しなければならない存在と考えた場合にはその通りなのかもしれませんが、その場合、組織はその管理職の理解や能力を超える技術や業務プロセスの導入が、できなくなってしまいます。果たして、そのような管理職が率いる組織が、現代の市場競争で勝ち残る事ができるのでしょうか?
本コースでは、リーダーシップスタイルの一つとして、サーバント・リーダーシップを学びます。サーバント(Servant)とは、使用人、召使いという意味であり、リーダーがフォロワーに奉仕する、支援型リーダーシップスタイルの事であり、前段に書いたような、部下を指導するスタイルとは全く異なるアプローチです。
今はVUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) 時代という、先行きが不透明で、将来の予測が困難な時代であり、サーバント・リーダーシップスタイルは、そのような環境で組織に所属するメンバーが有効なリーダーシップを発揮する、一つの答えである可能性はあります。
しかしながら、本コースにおいてサーバント・リーダーシップは、「大企業ではそれ程普及していないリーダーシップスタイル」とも言及されており、物事にはそれぞれメリット、デメリットがあるようです。
かつて、カーライル(Carlyle)はリーダーシップを、生まれながら持つ性質であるとし、他人より優れた資質を持った偉人がリーダーとなりえると定義しました。
しかしながらその後の研究により、効果的なリーダーシップスタイルは、状況、目標、メンバー等により異なり、また、リーダーシップスタイルは生まれもった性質ではなく、後から身に着ける事ができる能力である、という考え方が主流になってきています。
本コースでは、そのような過去から現在に至るリーダーシップ研究の歴史を学びますので、実際に自分の職務に置き換えて、管理職としても、フォロワーとしてもリーダーシップを発揮し、成果を出すための知識やヒントを学ぶことができます。
このような理論を学ぶときに思うのは、時代や国が違っても、人の集団である組織には共通した傾向があり、現代の日本の我々の実務においても役立つ知識が多いという事です。
とはいえ、真にリーダーシップを発揮するためには、知識を学ぶだけでなく、本当に他者や組織の事を思い、実際に行動を起こす必要があるとも思ったりします。
注意が必要なポイント
私はこれまで企業研修の一環として、リーダーシップ研修を受けたことがありますが、本コースで学ぶ内容も、理論は手厚くフォローされてはいるものの、おおよそ似たような内容だと感じました。
つまり、本コースも組織変革をリードする、リーダー人材を育成するためのカリキュラムであり、そこで期待されるリーダーとは、ビジョンと進むべき方向性を示し、かつ控えめであり、フォロワー(チームメンバー)に対しては思いやりと理解と共感をもって接する事が必要である、というものです。
これができるのは、伝記の中に登場する、偉人のような人だけかもしれませんね..。
我々が日々対応する実務の世界では、管理職は会社から短期的な成果も求められますし、フォロワーとなる部下へも甘い顔ばかりしていられないので、そのような理想と現実とのギャップに、どのように折り合いをつけて解釈していけるかが、「リーダーシップ」を学ぶ上で、注意が必要なポイントなのではないかと思います。
例えば、あるリーダーシップスタイルを学び、それらを発揮した事例を調査・研究掘り下げる事は、理論を解釈する上では役に立つかもしれませんが、実務で活かせるリーダーシップを学ぼうとする場合には、あまり参考になる気がしません。
なぜならば、効果的なリーダーシップスタイルは、時と場合により異なるからです。
反対に、リーダーシップの類型で見られる、パフォーマンスが低いチームの傾向や、各リーダーシップスタイルのデメリットに着目した方が、自分の実務にダイレクトに活用できるのではないかとも思います。
例えば、本コースではトランザクション(交換型)リーダーシップという、飴と鞭により、フォロワーを動機付けようとするリーダーシップスタイルを学びます。これはつまり、「あなたの昇給・昇格のために、今期の目標を達成しよう!」というようなリーダーシップスタイルの事ですね。
これは簡単でわかりやすいので、管理職としてやりがちなスタイルであり、短期的な目標の達成には効果的な場合があるかもしれませんが、チームメンバーの目線を全体像や将来計画に向け、組織としての革新や創造を求めようとする時には、不向きなリーダーシップスタイルであるとも言われています。
つまり、もし自分のリーダーシップスタイルがトランザクションリーダーシップに偏っていると思うのであれば、そのデメリットを補う方法を学習し、実務上での具体的な行動にまで落とし込んでいけば良いわけです。
これは推測ですが、何かしらの機会でリーダーシップを学んだとしても、実際に自分の行動を変えられる人は少ないのではないでしょうか。言い換えれば、それができる人は貴重な存在であり、後からリーダーシップを身に着けられる人であるような気がします。
国や時代を超えても語り継がれている人間や組織の傾向には、学ぶべきことが多いと思います。今は誰も正解がわからない時代ではありますが、先人から引き継がれている、人や組織が失敗する傾向には学ぶべきことが多く、素直に受け止めた方が良いような気がしております。
お役立ち情報
本コースは組織行動論(UoPeople MBA BUS 5113 Organizational Theory and Behavior 組織行動論コースレビュー)と重複する分野があります。
具体的には、組織行動論でも学ぶ「リーダーシップ」の深掘りが本コースの主テーマとなりますし、チームワークやモチベーションも、当然関係してきます。
そのため、本コースを受講する前に、組織行動論を振り返っておくと良いと思います。